東洋思想においては「中庸」=バランスがとれた状態が良いとして尊ばれます。
古代の人たちは、陰陽のバランスがとれた状態を「静」、偏った状態を「動」をつくると考えていたといわれているので、「中庸」を尊んだということは、「静」、つまり穏やかで平穏なことが幸せだと考えていたのだろうと思われますが、
一方で、何か変化を起こすとか成長する、進歩する、といったことを目指す場合には「動」が必要であったりもします。
その意味では「中庸を欠く」=アンバランスなこともときとして必要だということもまた認識していたであろうと思います。
(この辺りにも一極二元の考え方が見えますね。)
さて、この「動」と「静」の関係を、平和と動乱、停滞と進歩、攻めと守り、などに活用する理論を「静動理論」といいます。
『二つの世界がある一点において融合するとき、陽対陽、陰対陰は動をつくり、陰対陽、陽対陰は静をつくる』
…いう言葉で表されるこの理論は、六十干支を考える上では不可欠の理論です。
六十干支は陰の干には陰の支、陽の干には陽の支がつきますが、これは「万物は進歩する(動である)」という考え方によります。
この考え方は、他にも兵法などで応用されました。
例えば、疲弊した国(陰)がその国を再建するには「自力」(陰)による場合と他国の力(陽)による場合があります。
また、その再建を「緩やか」(陰)に行うか「急いで」(陽)行うかも分かれます。
この対応策は、
①自力(陰)✖️緩やか(陰)=陽=動
②他力(陽)✖️緩やか(陰)=陰=静
③自力(陰)✖️急いで(陽)=陰=静
④他力(陽)✖️急いで(陽)=陽=動
のように表すことができます。
軍略論では、『国の発展には動をもって是とする』といわれるので、再建策を考える場合は上記の4つのうち、「動」につながる①と④のやり方が効果的であるということになります。
では、「動」=偏ることを選んだ場合、中庸は要らなくなるのかといえばそうではありません。
例えば、他力で急いで再建する場合は陽✖️陽で偏りますが、その際に借りる「他力」をどの「他力」にするかを考えるときには「中庸」の視点が必要になります。
自国よりはるかに大きな力を持つ他力を借りてしまえば疲弊している自国は併合の危機、崩壊の危機にあうかもしれません。
そこにはバランス=中庸の視点が必要で、自国とバランスのとれた「他国」を選ぶ必要があり、つまるところ偏りの中にも中庸が登場するわけで、中庸というのはやはり常に必要である、ということになります。
ちょっと頭がこんがらがりそうですが、
平たくいえば、
何事においてもやり過ぎはよくなくて、やり過ぎたと思ったらどこかで抜きましょう。
やらな過ぎてもよくないので、やらな過ぎているならどこかでパンチの効いた何かをやりましょう。
…みたいな感じです。
現代に応用し、例えば受験勉強で考える場合、
①独学(陰)✖️緩やか(陰)=陽=動
②塾 (陽)✖️緩やか(陰)=陰=静
③独学(陰)✖️急いで(陽)=陰=静
④塾 (陽)✖️急いで(陽)=陽=動
ということになります。
これを説明すると、
①独学で勉強するならコツコツ継続的に勉強すると効果的。
②塾に長々通って勉強しているとだれてしまって肝心なときに力が発揮できなくなります。
③独学で一夜漬けをしたりどんどん進めてしまうと中身が空っぽだったりして効果なし。
④受験の年から塾に通うなら、そこだけは集中して(急いで)勉強すること。そうすれば効果が期待できます。
…というような感じでしょうか。
いろんな局面に応用できそうなので、覚えておくと良いだろうと思います。
※『悠久の軍略』高尾義政著 を参考にさせていただきました。

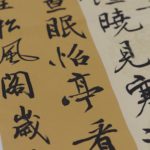
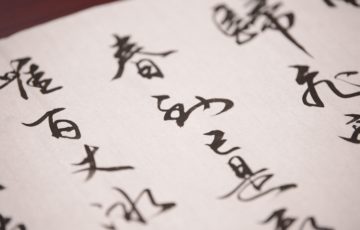
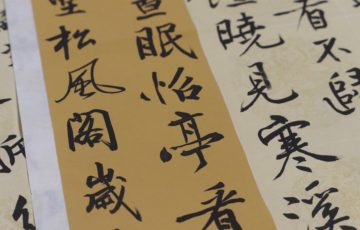
最近のコメント