古代東洋においては、世界(=地球)を東西南北中央に区分して、その四つの隅(東西南北を面として四角形を描いた場合の四隅)のうち、西北(戊亥=天門)から東南(辰巳=地門)にかけてのラインを大地の中心軸としてとらえていました。
この軸に直角に交わるラインが赤道で、その赤道と交わりながら、太陽、次の、そしてその他の惑星である水星、金星、火星、木星、土星(古代で認識されていたのはここまで)が通る道を黄道といいます。
この黄道のラインがおおむね北東から南西にかけて通過するラインであること、そして古代の人たちはそれらの太陽と月、五つの惑星を神様としてとらえていたことから、黄道のライン(=北東から南西のライン)を神様がとおる道筋だと考えたのだそうです。
そのため、北東を神様が通過する際の入り口(鬼門)とし、南西を神様が去っていく出口(裏鬼門)としてその方角をふさいだり、その通り道を汚いままにしたりすると、その家に鬼👹が入り込むといわれ、このラインを「神様の通り道」おして常にキレイに、清浄な場所にしておくという風習が根付いていきました。
※正東西南北は30度、戊亥、丑寅、辰巳、午未の四門は60度です。
なお、戊亥を天門、辰巳を地門(風門)、丑寅を表鬼門、未申を裏鬼門(人門、病門)と称し、これら四つの門をもって天と地の気を受け入れる方向としてとらえたそうです。
この考え方は、例えば毎年元旦に天皇陛下が四方拝の儀式(寅の刻に清涼殿の東庭で、天地四方を拝し、年災を払い五穀豊穣を祈られます)をしておられますし、一般的な社会でも、地鎮祭などで四方に結界を張ったりすることがあります。
これも、四方を祀って天と地の気を受け入れることにより様々なことを盤石にしていく、という意図があるのだろうと思います。
そう考えると、鬼門・裏鬼門のラインのみならず、天門・地門のラインも当然に尊く侵すべからざる場所であり、すべての方位、すべての四隅を同等に、平等に、大切にして清浄の気を保つことが望まれるように思います。
ちなみに、四方拝は、算命学と同じく道教の流れを汲むものといわれます。
日本では道教はあまり馴染みがないようにいわれますけれど、その実、習慣や風習の中には道教を元にしているものが多くあります。
鬼門についてWikipediaでもちらりと確認したのですが(情報はできるだけ2箇所以上で確認していきたいと思っています)、
みていて面白いな、と思ったのは、
「武家の世界では多くの城で鬼門方位に厠をつくるこおが常道とされていた」というお話。
安土城、丹波福知山城、岡山城、姫路城などは裏鬼門に厠が配されていたそうです。
これは、「鬼門の禍を恐れぬ覚悟をもった武将の気構え」なのだそうですが、さすが「戦国武将は下格が多い」といわれるとおり、下格の人のあるべき生き方とはまさに「神をも恐れぬ」生き方なのかもしれません。
但し、本人は「神をも恐れぬ」としても、大衆を率い、人心をまとめるためには「神を奉る」という「型」も大事だろうと思います。
このあたりに実は、安土城の鬼門に厠をつくった織田信長と、江戸城の鬼門に橋をかけるにあたり、位置は変えなかったものの名前を変えて人身に配慮した徳川家康を分けた遠因があるかもしれません。
よって、様々な価値観を持つ人たちを取りまとめるような立場の人であれば、鬼門に象徴されるような古来からの風習は大切するか、そうでなくても「型」を守ることはしておくと良いのだろうと思いました。
※『東洋の予知学』高尾義政著 を参考にしております。

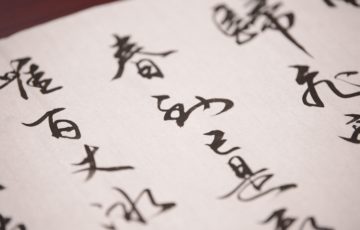
最近のコメント