東洋史観における気の概念の一つに、「坐気」というのがあります。
これは、いわゆる「坐」に宿る気のことで、何か役目を持つ人、何かの地位にある人など、そういう立場にある個々人が宿命や星図に持つ才能や能力に加え、その役割や立場、地位(=「坐」)に司る「気」、「力」が備わるのいわれます。
一人の個人が家庭を持ち、家長として長い年月を過ごすうちに、家長として相応しい能力なり風情なりの「気」を備えてくると、それは個人というよりは家長としての「気」が備わったものと考えます。
よく、「地位が人をつくる」といわれるのはそういう「坐気」を得て能力を発揮するという面もあるように思いますし、
例えば、万世一系といわれる天皇陛下の血統は125代も続いている「坐」の気なので、時として個人の宿命以上の力強さを持ってその「坐」を担わしめる力が働いているのではないかと感じられることもあります。
あるいは、医師の家系、政治家の家系というのも同様で、脈々と「坐」を継承しているような家系の場合、本人の宿命から見ると「おや?」と思うような面があっても、その役割を無事に勤め上げたりする、それはやはり「坐気」によるのだろうと思います。
なお、こうした地位などに備わる気のほか、家が山の中や海のそばにあると、
海の近くに住む人は海の気を受けて海人らしい考え方や能力を備えてくる、
あるいは山の近くに住む人は山の気を受けて山人らしい考え方や能力を備えてくる、
そういうことも一つの「坐気」として考えます。
こうした「坐」に宿る気というのは、時として本人の宿命を超えて人を動かすこともあるので、命式を拝見する場合にはそうしたことにも気を配る必要があります。
なお、算命学の「気」とは何か?
ということについて、高尾宗家は次のように書かれています。
…..
①東洋における思想的概念の一つで、「気を配る」「気をつかう」などに見られるような無形のエネルギーのこと。
主に精神的なもので、人間が発する磁場、あるいは磁力のようなもの。
(算命学を学び、人の命式を拝見していると、「あー、この人は渦巻きに巻き込まれているな」とか、「この人は何か引力によって導かれているな」と感じることがありますが、そういうことも含むのかな?と思いました。)
②気の概念は、自然の事物を陰陽説思考により解釈したところに始まる。
一本の樹木を陰と陽に分け、一方を樹木🌳そのものの形、もう一方を樹木が持つ魂と考える。
形から生まれるものは有形現実であり、魂は無形で精神のようなものである。
その魂の部分を捉えて「樹木の気」という。
ゆえに、人間の気と樹木の気とがある接点で融和するとき人間は感応する。(=「気」が合う)
人間をはじめ他の動物や事物のすべてに形と魂があると考えたところに「気」の概念の出発点をみることができる。
それゆえ、東洋では「気」を神格化して御神木や山の神、海の龍神など、気の信仰が生まれた。
この思考方法は、単一神信仰ではなく、宇宙即神の思考となり、多神信仰の根源となった。
…..
特に②はピンとこない人もいるかと思いますが、そもそも五行の考え方は、目に映るすべてに神が宿る多神教的な視点をもとに考案されたものなので、これも一つの「古代人の視点」「古代人の考え方」として、東洋思想を学ぶ上では絵空事として片付けることなく、現実的事象の一つとして捉えていく態度が求められるように思います。
即物的、唯物論的な価値観が席巻した時代を経て、現代は精神性の大切さも再評価されつつあります。
今はその過渡期にあるのかもしれません。
今、これをご覧くださった方は、心のどこかにこうした考え方を留め置いておかれると良いだろうと思います。
※『東洋の予知学』高尾義政著 を参考にさせていただきました。
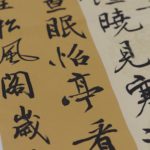
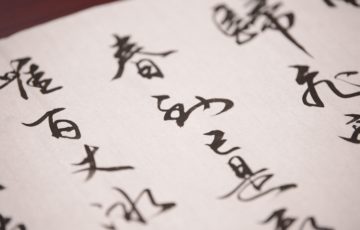
最近のコメント