十二支とは、陰陽五行説における「時間が通過する方向」を示す符号です。
一般的に十二支といえば、ねずみ→うし→とら→うさぎ…という動物を思い浮かべますが、これはこの符号を大衆が覚えやすいように便宜上付けられたあだ名のようなもので、その本質は動物とはなんの関係もありません。
実際、十二支の漢字はどれも実際の動物を示す漢字とは少し異なります。例えば、虎ではなく寅、馬ではなく午、などです。
さて、「時間が通過する方向」といってもピンとこないと思うのですが、これを理解するには、古代中国の人たちの思考を考える必要があります。
古代には時計がありませんでしたので、時間を示す言葉がありませんでした。そのため、「太陽が通過する方位」を「時」として認識し、その「太陽が通過する方位」の動き(幅)をもって時間として認識したのだそうです。
例えば、「午の刻」というのは太陽が午の方向=真南を通過する時間というふうに認識しました。よって「午の刻」は今の「12時きっかり」ではなく、「12時頃」ということで、その幅は約2時間ほど。
今の時代、2時間の幅で待ち合わせをすることはほとんどありませんが、そう考えると、古代の人たちはおそらく今よりずっとゆるやかで余裕のある時間の中で過ごしていたのであろうと思います。
そんなわけなので、算命学には四柱推命で使われる時柱がありません。
上記を理解すれば、十二支が「時間と方位」の両方を示すものであることも容易に理解できます。
なお、東西南北はそれぞれ卯、酉、午、子がその「時間と方位」を司りますが、東北、東南、西南、西北はそれぞれ丑寅、辰巳、未申、戊亥と2つの十二支をセットで使います。
これはなぜかといえば、丑、辰、未、戌の4つの十二支は土性なので、本来方位を持たない(土性は中央なので)ためです。
※なぜこれらが中央に置かれなかったかの原理はまた改めて書きます。
十二支はそれぞれ陰陽五行に分けることができます。
木性→陽寅、陰卯
火性→陽午、陰巳
土性→陽戌辰、陰丑未
金性→陽申、陰酉
水性→陽子、陰亥
ここにも「一極二元」の考え方が見えますね。陰陽双方を持って一とする考え方は、東洋思想を深く学ぶ上で不可欠の思考です。
なお、思想の世界における十二支は、陽が天空、陰が地上を示しています。そして、天と地は2つそろってはじめて一つの世界を構成します。
ちなみに、十二支は「太陽が通過する方位」であると書きましたが、1日の中で「太陽が通過する方位」を時間として認識した考え方は、一年の中で「太陽が通過する方位」をもって季節として認識する考え方につながっています。
亥を初冬、子を仲冬、丑を季冬、寅を初春、卯を仲春、辰を季春、巳を初夏、午を仲夏、未を季夏、申を初秋、酉を仲秋、戊を季冬といいます。
今も「仲秋の名月」など使われることがありますね。
※『東洋の予知学』高尾義政著 を参考にしております。
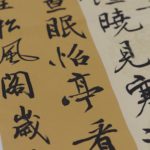
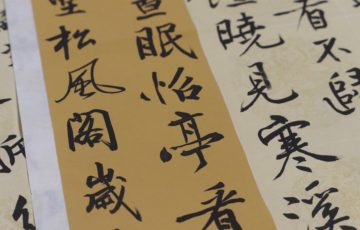
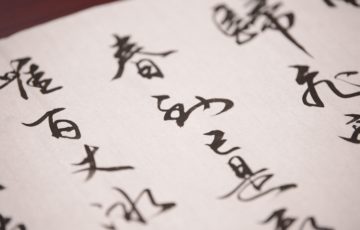
最近のコメント