東洋医学などにおいて、内蔵と五行、五官と結びつくのをご存知の方も多いと思います。
五官は体の身体の器官のことですが、「五官」という言葉を知らなくても、見れば分かる人もおられると思います。
肝臓=木性=聴覚(耳)=守備力
心臓=火性=味覚(口)=伝達力
脾臓=土性=触覚(皮膚)=引力
肺臓=金性=嗅覚(鼻)=攻撃力
腎臓=水性=視覚(目)=習得力
例えば、肝機能の強弱の分析には耳の形をみるとか、心臓の強弱をみるには口の形を利用す流といった形で利用されたりしています。
これらは算命学の源流である道教の原典の一つといわれる『黄帝内教』にあります。
よって、算命学を学ばれる方は、その理解と視野を広げるため、余裕があればこうした書籍にも触れてみると良いだろうと思います。
なお、例に挙げたような結び付けの技術を専門的には「偏官法」というそうですが、これは日常にも応用できます。
例えば人の目というのは人に会えば必ず見えるものですが、この目の形によってどの五行が強いかを知ることができます。
目の形には4つの形があるといわれます。
湿眼、燥眼、寒眼、暑眼の4つ。
一重瞼の細い目を寒眼といい、体が冷えやすい人です。
一方、大きな丸い目は暑眼といい、体が熱くなりやすく、火照りやすいといわれます。
目尻の下がった目を湿眼といい、体に水が溜まりやすい、体の水が濁りやすい、むくみが生じやすい人で、
目尻の上がった目は燥眼といい、これは「燥じる」つまり体内の水を乾燥させる=体内に水気が足りない人だそうです。
ご自身を振り返ってみていかがでしょうか?
ちなみに、これに五行を重ねると、
寒眼は習得力(水性)、暑眼は伝達力(火性)、湿眼は守備力(木性)、燥眼は攻撃力(金性)の質を持ちます。
カタチだけではピンと来なかった方も、五行を重ねると、「なるほど」と思われた方も多いのではないかと思います。
ちなみに、指にも五行があります。
親指が木性、人差し指が火性、中指が土性、薬指が金性、小指が水性です。
私は小指に指輪をするのが好きなのですが、
(それも、ピンキーリングとして売っている華奢で可愛いものでなく、割と大きめのもの)
小指が習得力の水性と知って、面白いものだなぁと思いました。

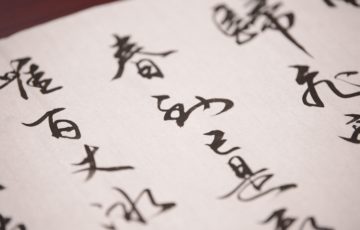
最近のコメント